10年以内に相続が続いたら相続税の負担を軽減できます【相次相続控除の計算方法】
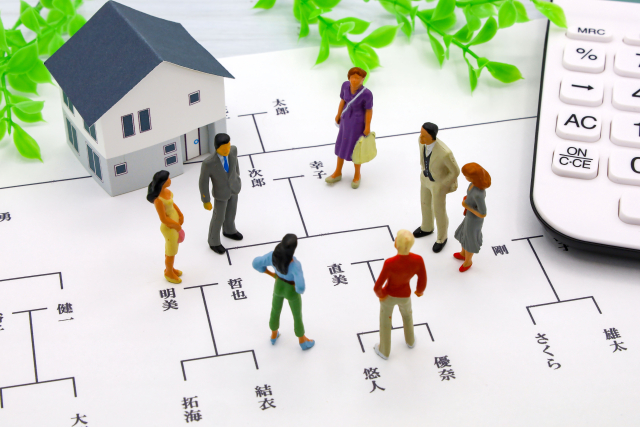
厚木市で 相続 の手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。
相続 の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。
「相次相続控除」は、10年以内に2回以上の相続(相次ぐ相続)があった場合に、2回目の相続(今回の相続)で納める相続税から、一定の金額を差し引くことができる制度です。
短期間での連続した相続から、ご遺族の税負担を軽減する制度です。
前回は制度の仕組みを説明いたしましたので、今回は計算方法や注意点について述べていきます。
計算で重要な要素
相次相続控除では、どれくらいの金額が控除されるのでしょうか。ここでは仕組みと考え方を簡単にご紹介します。
控除額を決める要素は、大きく分けて3つあります。
※今回も第一次相続でお父様が亡くなり、お母様が財産を相続。第二次相続でお母様が亡くなり、お子さんが財産を相続というパターンで解説します。
- ①お母様が「1回目(お父様)の相続で支払った相続税額」
これが全ての計算のベースとなります。やはり、ここがゼロだと控除額もゼロです。(そもそも控除適用されません。)
②1回目の相続から2回目の相続までの「経過年数」
相次相続控除は、2回の相続が近ければ近いほど、控除額が大きくなります。
具体的には、1年経過ごとに10%ずつ、控除できる割合が減っていきます。
③お母様が引き継いだ財産と、今回あなたが引き継ぐ財産の割合
「お母様がお父様から引き継いだ財産額」と、「今回あなたがお母様から引き継ぐ財産額」のバランスも考慮されます。
簡単に言えば、「お母様がたくさん相続税を払っていても、今回あなたが相続する財産が少なければ、控除額もそれに応じて少なくなる」という調整が入ります。
相次相続控除の計算方法
控除額の実際の計算式は以下の通りです。
各相続人の相次相続控除額=A×{C/(B-A)}×(D/C)×{(10-E)/10}
※C>(B-A)の場合、C/(B-A)を1として計算する。
- A:第二次相続の被相続人が第一次相続で課税された相続税の金額
※相続時精算課税等の贈与税額控除後の金額で、延滞税などの加算税額は含みません。 - B:第二次相続の被相続人が第一次相続で引き継いだ純資産の価額
※「取得財産の価額+相続時精算課税適用財産の価額-債務および葬式費用の金額」で計算。 - C:第二次相続で財産を取得した相続人全ての純資産価額合計
※遺贈・相続税課税対象の贈与も含みます。 - D:第二次相続でのその相続人の純資産価額
- E:前の相続から今回の相続までの年数
※1年未満は切り捨てとなります。
既に述べましたが、1次相続と2次相続までの年数が短いと控除額が上がります。
これは、制度の目的が短期間での税負担軽減だからです。
相次相続控除の注意点
(1)「申告」しなければ適用されない
相次相続控除は、自動的に適用されるものではありません。2次相続での相続税申告の際に、「相次相続控除を適用します」という意思表示と、控除額の計算明細書を「相続税申告書」に添付して提出する必要があります。
ただし、後の更正の請求の際に申請しても問題ありません。
(2)1回目の「相続税申告書の控え」が必須
税務署に適用要件の証明のために、第一次相続の際の「相続税申告書の控え」が必要になります。よって、前回の相続関連の書類を、捨てずに保管しておきましょう。
(3)遺産が未分割状態でも適用できる
相次相続控除は遺産分割協議が完了していなくても適用できます。
適用する場合は、法定相続分に従って一時的に2次相続の相続税を算出します。
(4)特例の適用は各相続人で選択する
控除の適用は2次相続の相続人が自由に選択できます。つまり、控除は個々人の権利であり、各相続人が控除額を振り分けるといったことはできません。
他の相続人が適用しなかったからといって、その控除分を別の相続人が代わりにもらうことは不可能です。
数次相続との違い
相次相続と数次相続の二つは「立て続けに相続が起きる」点で似ていますが、「前の相続手続きが終わっていたかどうか」で異なります。
- 相次相続→手続きが「完了した後」に次の相続が発生
- 数次相続→手続きの「途中」で次の相続が発生
相次相続とは一次相続の手続き(遺産分割や相続税の申告・納税)が全て完了してから、10年以内に次の相続が起きた場合を指します。
家族で遺産分割を終え、お母様が相続税も納めてお父様の相続の手続きがすべて完了。
その3年後に、お母様が亡くなる(二次相続)。
この状態が「相次相続」であり、「相次相続控除」が使える可能性があります。
数次相続とは一次相続の手続き(遺産分割協議)が終わらないうちに、相続人の誰かが亡くなってしまい、二次相続が始まってしまう状態です。
例えば、お父様が亡くなる一次相続で遺産の分け方を家族(母・長男)で話し合っている最中に、お母様が亡くなる(二次相続)と、お父様の遺産分割協議は、長男が1人で決めることになります。
数次相続であっても2次相続で亡くなった人(例:お母様)が、1次相続で相続税を(計算上)課税されていれば、相次相続控除が適用できます。
まとめ
相次いでご家族を亡くされるという大変な状況の中で、税金の手続きを進めるのは精神的にも大きなご負担かと思います。
相次相続控除は、そのようなご遺族の負担を少しでも軽くするために作られた、正当な権利です。
ただし、適用できるかどうかの判断(特にお母様が税金を払ったか)や、実際の控除額の計算は、相続財産の内容が複雑になるほど難易度が上がります。
「うちは使えるのだろうか?」「いくら安くなるのだろう?」と思われたら、お一人で悩まず、相続専門の税理士にご相談ください。ご家庭の状況に合わせた最適な申告をサポートいたします。
相続の手続きでお困りのことがございましたら、相続手続の専門家・相続手続相談士のいる厚木相続相談センターまでお気軽にご連絡ください。
行政書士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士との強いネットワークを活かして、あなたの相続の悩みをサポートいたします。
まずはお気軽に初回無料相談をご利用ください。
■お問い合わせフォームから今すぐ初回無料相談をしたい方→こちらをクリック
■お電話で今すぐ初回無料相談をしたい方→046-297-0055(受付時間:平日9:00~17:00)

1960年東京生まれ 早稲田大学商学部卒業
1989年税理士登録
相続手続きについての執筆活動もしているエキスパート。
複数の事務所勤務を経験後、1995年厚木市に税理士事務所開業。2015年法人設立、代表就任。
税務や会計にとどまらず、3C(カウンセリング、コーチング、コンサルティング)のスキルを使って、お客様が幸せに成功するお手伝いをしています。
■著書
「儲かる社長がやっている30のこと」(幻冬舎)
■執筆協力
「相続のお金と手続きこれだけ知っていれば安心です」(あさ出版)
「事業の引き継ぎ方と資産の残し方ポイント46」(あさ出版)
その他多数。
